まずは無料でご相談ください
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。

「うちの会社は上場していないから、株価なんて関係ないよ」
そう思われる中小企業の経営者の方もいらっしゃるかもしれません。確かに、市場で日々株価が変動する上場企業とは異なり、非上場企業の株価は、普段意識する機会はあまりないかもしれません。
しかし、将来を見据えたとき、特に事業承継を検討する際には、自社の株価を把握しておくことが非常に重要となります。
例えば、後継者への株式譲渡や、M&Aによる会社売却などを考える際、適正な株価をしらなければ、予期せず不利益を被る可能性も。また、親族内承継の場合でも、相続税や贈与税の計算において、株価が大きな影響を与えるため、事前の綿密な準備が不可欠です。
ここでは、非上場企業の株価を算出するための代表的な方法をご紹介します。
目次
非上場企業の株価算出の方法を見ていく前に、まずは株価に関する基本的な知識を確認しましょう。
■株価とは何か?
「株価」とは、一般的に株式が取引されるときの価格を指します。上場企業の場合、株式を買いたいと考える投資家(需要)と、売りたいと考える投資家(供給)のバランスによって決まります。
買いたい人が多ければ株価は上がり、売りたい人が多ければ株価は下がるという、いわゆる市場原理が働くことで、適正な価格が形成されると考えられています。
一方、非上場企業の場合、証券取引所のような公開された市場で自由に取引されるわけではありません。そのため、客観的な市場価格というものが基本的に存在しないという点が、上場企業との大きな違いです。
では、非上場企業の株価は、どのように考えればいいのでしょうか。
非上場企業の株価は、市場での取引がないため、一律に決まった価格はありません。その代わり、企業の現在の状況(業績や保有する資産など)はもちろんのこと、将来の成長性や収益力、そして業界の動向や経済状況など、多岐にわたる要因を総合的に考慮して算出する必要があります。
そのため、非上場企業の株価算出は、上場企業の株価のように単純なものではなく、様々な評価方法が存在し、その目的によって適切な方法を選択する必要があります。
■株価算出の目的別アプローチ
非上場企業の株価を算出する目的は、一つではありません。どのような目的で株価を知りたいのかによって、重視すべき要素や適切な算出方法が異なってきます。
ここでは、中小企業において、株価算出が必要となる主なケースをいくつかご紹介します。
このように、株価算出の目的によって、どの要素を重視し、どのような方法を用いるべきかで変わってきます。


非上場企業の株価を知ることの重要性とその特徴についてお伝えしましたが、ここでは、代表的な非上場企業の株価算出方法をいくつかご紹介します。
類似業種比準方式は、事業内容や規模、収益構造などが類似する上場企業の株価指標を参考に、自社の株価を算出する方法です。
上場企業の株価は市場で評価されているため、ある程度の客観性を持つと考えられています。
■計算方法の概要
類似業種比準方式では、主に以下の株価指標を用います。
・PER(株価収益率):株価を1株あたりの当期純利益で割ったもの。企業の収益力に対する市場の評価を示します。
→計算例:類似上場企業のPERの平均値×自社の1株当たりの当期純利益
・PBR(株価純資産倍率):株価を1株あたりの純資産で割ったもの。企業の資産価値に対する市場の評価を示します。
→計算例:類似上場企業のPBRの平均値×自社の1株あたりの純資産
これらの指標を、類似する上場企業の平均値などを用いて、自社の財務状況に掛け合わせることで株価を算出します。
純資産方式は、企業の賃借対照表に記載されている純資産額をベースに株価を算出する方法です。
会社の持つ資産から負債を差し引いた金額が、株主にとっての持ち分であるという考え方に基づいています。
■計算方法の概要
純資産方式には、主に以下の2つの考え方があります。
・簿価純資産:賃借対照表に記載されている帳簿上の価格(簿価)で評価された純資産額をそのまま株価とする方法
→計算例:(総資産 – 総負債)÷ 発行済株式総数
・時価純資産:保有する資産(不動産、有価証券など)を時価で評価し直した上で、純資産額を算出する方法
→計算例:(時価評価した総資産 – 総負債)÷ 発行済株式総数
収益方式は、企業の将来の収益予測に基づいて株価を算出する方法です。
将来的に企業が生み出すであろうキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り引くことで株価を評価します。代表的な方法としてはDCF法があります。
■計算方法の概要
DCF法では、まず企業が将来生み出すと予測されるキャッシュフローを複数年分予測します。
次に、その将来のキャッシュフローを、企業のリスクなどを考慮して設定した割引率で現在価値に割り引きます。
割り引かれた将来のキャッシュフローを合計することで、企業の事業価値を算出し、そこから負債などを調整することで株価を算出します。
それぞれの方法には、メリットとデメリットがあり、企業の状況や株価算出の目的によって、適切な方法を選択する必要があります。
実際に株価を算出するとき、いくつかの重要な注意点があります。また、状況によっては、専門家のサポートが不可欠となることもあります。ここでは、株価算出における注意点と、専門家活用の重要性についてまとめました。
非上場企業の株価算出は、上場企業の株価のように市場原理によって決まるものではないため、特有の難しさがあります。
■市場での取引がないことによる客観性の欠如
上場企業の株価は、多くの投資家の判断によって形成されるため、ある程度の客観性があります。
一方、非上場企業の株価は、算出方法や評価者の判断によって大きく左右される可能性があり、客観的な価格を見出すことが難しい場合があります。
■将来予測の不確実性
収益方式など、将来の予測に基づいて株価を算出する方法では、その予測の正確性が株価に大きな影響を与えます。
しかし、将来の経済状況や市場動向、企業の業績などを正確に予測することは非常に困難です。
■評価者の主観が入りやすい
どの算出方法を選択するか、また、各算出方法における具体的な数値(類似企業の選定、割引率の設定など)をどのように判断するかによって、評価者の主観が入り込む余地があります。
上記のような難しさがあるため、非上場企業の株価を算出する際には、以下の点に注意する必要があります。
■目的を明確にする
まず、何のために株価を算出するのかという目的を明確にすることが重要です。事業承継、資本政策、相続など、目的によって適切な算出方法や重視すべきポイントが異なります。
■複数の算出方法を検討する
一つの算出方法だけで判断するのではなく、複数の方法を試算し、それぞれの結果を比較検討することが望ましいです。異なる視点から株価を評価することで、より多角的な判断が可能になります。
■企業の状況を総合的に考慮する
株価は、企業の過去の業績や現在の財務状況だけではなく、将来の成長性や属する業界の動向など、様々な要素を総合的に考慮して判断する必要があります。
■税務上の影響も考慮する
特に事業承継や相続・贈与を目的とする場合、株価の評価額が税金に大きく影響します。税務上のルールや評価方法を理解し、税理士などの専門家と相談しながら進めることが重要です。
非上場企業の株価算出は、複雑で専門的な知識を必要とする場合が多く、自社だけで正確な株価を算出することは難しいかもしれません。そのような場合には、専門家の力を借りることを強くおすすめします。
■客観的な評価とアドバイス
税理士や公認会計士などの専門家は、客観的な視点から企業の状況を分析し、適切な株価評価方法を選択してくれます。また、算出された株価の妥当性や、今後の対応についてのアドバイスを受けることができます。
■複雑な計算や手続きのサポート
収益方式のような複雑な計算や、評価に必要な書類の準備など、煩雑な手続きを専門家がサポートしてくれるため、経営者は本業に集中することができます
■税務上のリスク軽減
税務の専門家である税理士に相談することで、税法上のルールに則った適切な株価評価を行い、将来的な税務リスクを軽減することができます。また、事業承継や相続に関する税務対策についてもアドバイスを受けることができます。
株価算出は、企業の未来を左右する重要な判断材料の一つです。自社の状況を正確に把握し、必要に応じて専門家の力を借りながら、慎重に進めていきましょう。


株価算出は、単なる数字の計算ではなく、企業経営における非常に重要な要素です。
非上場企業の株価を算出する方法は複数存在し、それぞれに特徴があります。大切なのは、株価を算出する目的を明確にし、その目的に合った適切な算出方法を選択することです。
ただし、非上場企業の株価算出は、専門的な知識や経験が必要となる場合も少なくありません。より正確な評価が必要な場合は、税理士や公認会計士、M&Aアドバイザーなどの専門家のサポートう受けることをおすすめします。
売却価格を60秒でシミュレーション基本的な財務情報を入力すると、WEB上で会社の売却価格を自動で算定します。
各業界の動向や調査統計情報、株式市場、M&A市場の動向を総合して
売却価格を計算します。
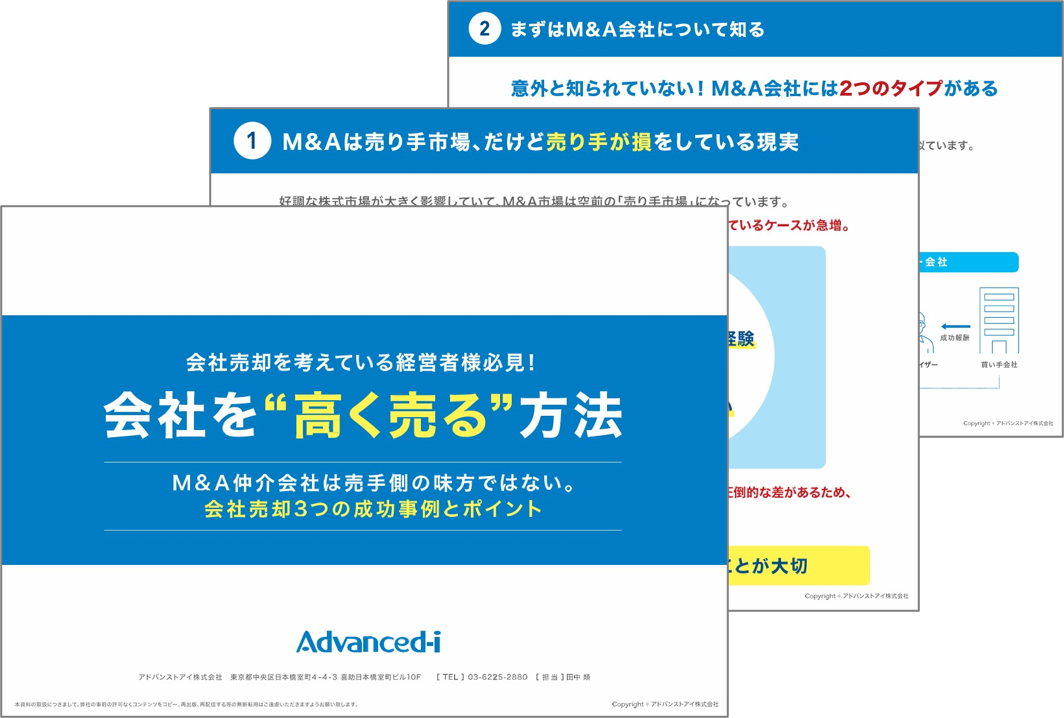
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。