まずは無料でご相談ください
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。

会社を売却した後、同業種で新規にビジネスを始めることは可能なのでしょうか。
M&Aによって会社を売却したX氏は、その資金を元手に新会社を設立しました。しかし、競業避止義務に抵触することを考慮し、新会社の役員には就任しませんでした。にもかかわらず、X氏は3000万円の違約金を支払うことになってしまったのです。
競業避止義務に違反する意図はなかったにもかかわらず、なぜX氏は違約金を支払う事態に陥ったのでしょうか。その背景について詳しく見ていきましょう。
X氏は、自身が経営していたインターネット通販会社をある大手企業に売却しました。
この譲渡契約には、「譲渡後5年間、売り手は買い手と同種の事業に関与しない」という競業避止義務が明記されていました。これは、会社売却後、一定期間は同業のビジネスに携わることを禁じるものです。
しかし売却から1年後、X氏はM&Aで得た資金を元手に、新たなインターネット通販会社を設立します。競業避止義務の存在を認識していたX氏は、新会社の株主にはなったものの、役員には就任しないことで契約違反を回避できると考えました。
ところが、買い手企業はX氏の新会社への関与を察知し、競業避止義務違反であると主張。その結果、X氏は譲渡契約に基づき、3000万円の違約金を支払うことになりました。


高齢や後継者不在による事業承継では、オーナー経営者が競業避止義務に抵触する行動を取ることはほとんどありません。多くの場合、買い手企業の恩義を損なうような行為は慎まれます。
しかし、40代・50代で早期に事業を譲渡したりするケースでは事業が異なります。一旦事業から離れても「もう一度仕事がしたい」と考える人は少なくありません。
売却時には「同業には二度と関わらない」と思っていても、新たな一歩を踏み出す際、これまでの経験を活かせる同業種のビジネスに魅力を感じてしまうのは自然な流れかもしれません。
そのためか、譲渡契約に3年や5年といった競業避止義務が定められているにもかかわらず、その重要性を軽視し、同業のビジネスを始める人が後を絶ちません。
「経営陣に入らなければ問題ない」
「株主としての出資だけなら違反にならない」
「商圏が異なれば関係ない」
このような自己判断に基づく誤解が、トラブルの原因となることがあります。しかし、売り手企業の思いを受け継ぎ、事業を承継した買い手企業にとって、これらの行為は到底容認できるものではありません。
もっとも、完全に同じ事業を再び展開するような無謀な行動は少ないでしょう。問題となりやすいのは、
・以前の事業の周辺分野への参入
・過去の取引顧客に対する、形を変えた商品やサービスの提供
といった、「完全に同一ではないから問題ない」という安易な判断です。
このようなトラブルを避けるためには、買い手企業と細部に至るまで確認を重ねて、認識の齟齬がないように慎重に進めることが不可欠です。
競業避止義務の範囲を巡る判断は、非常に難しいものです。例えば、売却した会社の主要顧客に対し、異なる業態でアプローチしたい場合、どのように考えるべきでしょうか。
「まったく別の業種だから問題ない」と安易に判断するのは危険です。主要顧客リストは、役員として知り得た重要な機密情報に該当する可能性があります。それを流用すれば、売り手企業の役員としての注意義務違反とみなされ、会社のステークホルダーとの関係悪化を招く恐れもあります。したがって、顧客への働きかけは慎重に行うべきです。
また同業種で新たなビジネスアイデアを着想した場合、
・買い手企業との競業を検討する
・正式に買い手企業の許諾を得る
このように、リスクのない形で進めるのが賢明です。
日本の中小企業におけるM&Aでは、契約書に詳細な条項が盛り込まれないことも少なくありません。そのため、「契約書に明記されていないから問題ない」と独断的に解釈すると、違約金の支払いというリスクにつながりかねません。
M&Aは、売却をもって終わりではありません。売却後の行動にも制約があることを認識し、慎重に対応することが大切です。
売却価格を60秒でシミュレーション基本的な財務情報を入力すると、WEB上で会社の売却価格を自動で算定します。
各業界の動向や調査統計情報、株式市場、M&A市場の動向を総合して
売却価格を計算します。
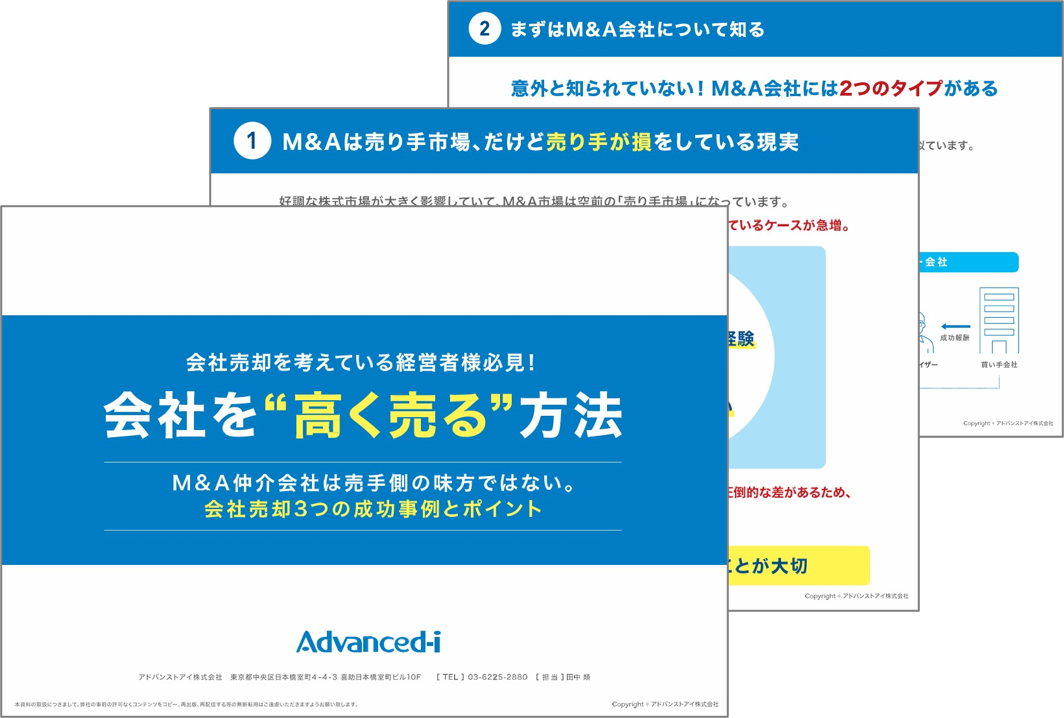
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。